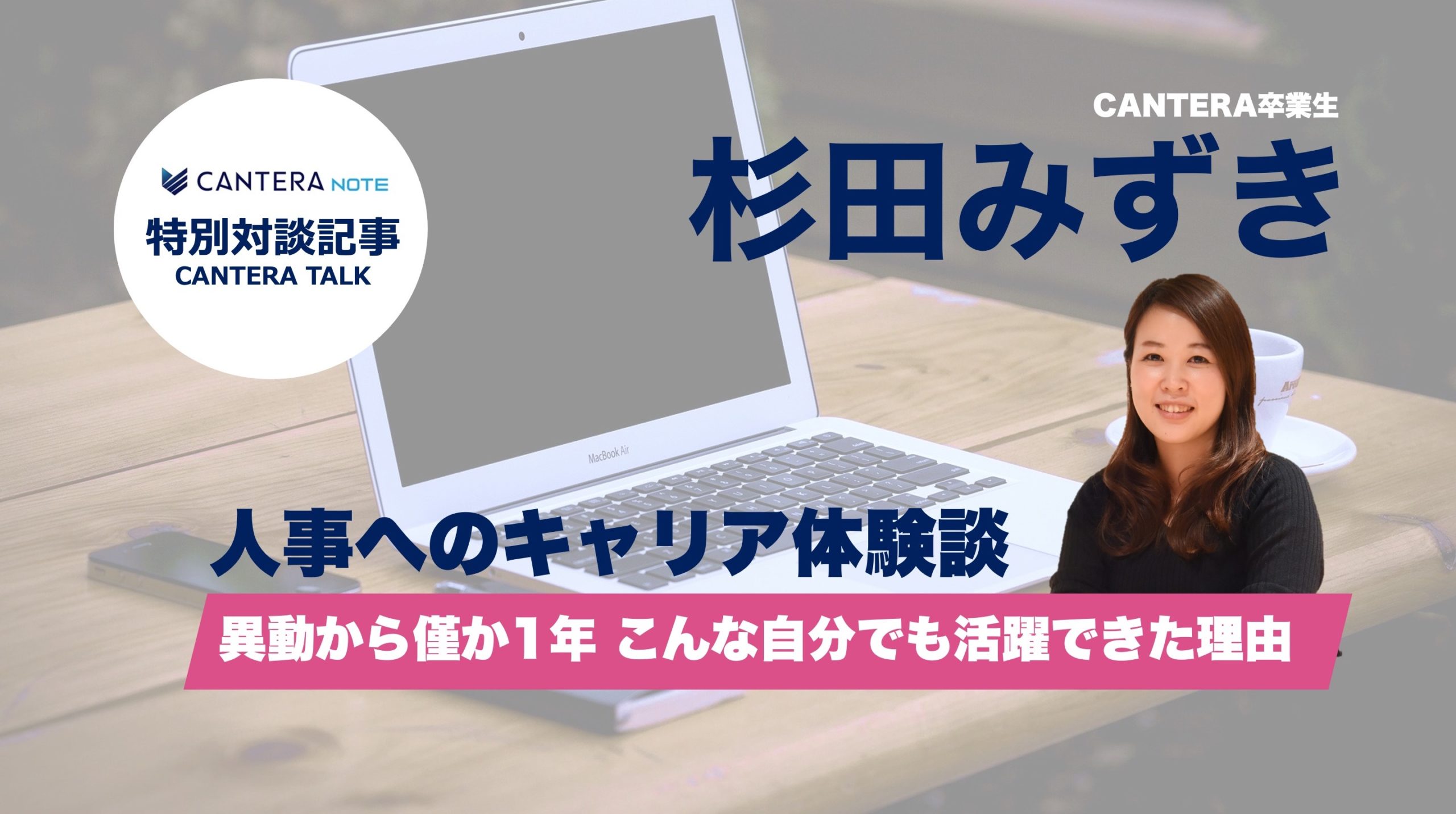人材エージェントとリレーション構築の必要論

人材エージェントとは
正式には「有料職業紹介事業」を営む人や企業を指します。事業をするには、有料職業紹介事業申請を国へ行う必要があり、許可を得ている場合は、各社Webサイトに厚生労働大臣許可番号というものが載っています。
採用したい企業と仕事を探している求職者との間に立って、企業から求人を預かり、転職(就職)希望者に対して転職先の紹介や仲介に関わるビジネスです。よくリボン図に表現されたりします。
図1 エージェントリボン図①
たくさんあるエージェント
現在、人材エージェントは厚生労働大臣許可番号を得ている事業所数をみると、全国で27,300 件ヒットしました。(厚生労働省職業安定局 人材サービス総合サイトより)
正直こんなにあると、どこに求人を依頼したらいいかわからなります。あくまで私見ですが、エージェントの特徴を分類分けしてみました。
1.大手総合型:幅広い業界、求職者層の紹介が可能。紹介数は多い。
例えば、以下のようなエージェントがあります。
・リクルートエージェント(国内人材大手のリクルートキャリア社が運営)
・doda(国内人材大手のパーソルキャリア社が運営)
・マイナビエージェント(統合ブランド「マイナビ」を展開するマイナビ社が運営)
・Spring転職エージェント(世界最大級の人材サービス企業アデコ社が運営)
2.特化型:特定の分野に強いエージェント。
例えば、以下のようなエージェントがあります。
・Geekly(IT/Web業界に特化)
・レバテックキャリア(IT/Web系エンジニアに強い。レバレジーズ社のグループ会社が運営)
・Re就活エージェント(20代・第2新卒に特化しているエージェント。あさがくナビの学情社が運営)
・MS-Japan(バックオフィス職に特化)
・JAC recruitment(ミドル・ハイクラスに特化)
・コトラ(金融、IT、コンサル、製造業、経営層の紹介に特化)
3.ヘッドハンティング型:ハイキャリア人材のヘッドハンティング。サーチングのため前金が必要な会社もあります。
例えば、以下のようなエージェントがあります。
・リクルートエグゼクティブエージェント(リクルートグループのヘッドハンティング会社)
・エンワールド(外資やハイクラスに強いエン・ジャパンのグループ会社)
・サーチファーム・ジャパン(伊藤忠商事クループのヘッドハンティング会社)
4.外資系企業型:バイリンガル人材の紹介に強い外資系エージェント。
例えば、以下のようなエージェントがあります。
・RGF(アジアを中心に日本を含め11の国と地域26都市展開する。リクルートグループ)
・ランスタッド(世界39か国に拠点を持つ)
・RobertWalters(世界31カ国の主要都市にオフィスを構える)
・マイケル・ペイジ(外資を中心に内資企業も紹介するグローバルネットワークがある)
5.独自型:エージェント自身の人脈や独自の方法で集客しているようです。元々エージェントにいた方や企業人事だった方が独立していたりと、色々な方がいらっしゃいます。少人数で事業をしているエージェントに多い印象で、マッチング率は総合型と比較をすると高いが、紹介数は少ない感じがしています。
6.エージェントのプラットフォーム型:採用企業は求人票を入力しておくと、個別に契約をしなくても中小エージェントを中心に人材を紹介してくれるサービス。前課金なく幅広いエージェントに求人がシェアできるので効率的ですが、直接エージェントとやり取りしない分しっかりと情報を記入しておく必要があります。
例えば、以下のようなサービスがあります。
・CrowdAgent(2700名以上のエージェントが登録し8000社以上が利用しているプラットフォーム。成功報酬は採用時理論年収×35%~)
・JoBins(2018年2月開始のプラットフォームサービス。採用成功フィーが元々は低め設定可能でしたが、変わってきているようなので興味があれば問合せしてください。)
エージェントとの握り
それぞれの特徴をもとに、どのエージェントに依頼をするか決め、エージェントとの契約を行ったら、担当のエージェントと打ち合わせです。ポイントは、以下5点です。
- 業界の理解
- 企業の理解
- 職種の理解
- 面接官の特徴や見ているポイントシェア
- 共通の目標をもつ
≪具体的な施策≫
1.業界の理解は、大手エージェントも業界別担当制になっていたりするので一定レベルは持っている担当者もいますが、非上場企業はHPや四季報にある情報以外にエージェントも事前情報が手に入りづらく、事前の調査不足の場合もあるので、自社の業界内での位置づけ等をシェアすると、エージェント自身にもイメージいただけます。
2.企業の理解は、1.にもつながりますが、自社の特徴を3C分析・4P分析を行い、できるだけ幅広めに要素(製品は○○業界トップシェア、役員が有名人、組織図、自社の顧客、顧客に支持される理由、資金調達した、表彰された・メディアに出た等)を伝えます。このとき、トップシェアに関してはエビデンスも必要だったりするので、準備しておくといいと思います。
また、エージェントは事前に調べたことからより深堀した情報を質問してヒアリングしてくれますので、エージェントが知りたいことをしっかりお伝えするのもベターです。勘のいいエージェントは、この情報で求職者に響く魅力ポイントを絞り込んでくれます。
3.職種の理解については、同じような職種でも関わる範囲が異なっているので会社によって異なります。人事も現場スタッフから事前にヒアリングしておくといいと思います。
また、エージェントとの打ち合わせに同席いただくのも手です。この際、“5W1H+仕事のやりがい”で仕事内容を整理し、求める人物像に関しては“必須条件・尚可条件・歓迎条件”の3軸を整理しておくとエージェントとも共有しやすいです。
4.面接官の特徴や見ているポイントを共有しておくことも重要です。せっかく紹介しても面接でうまくいかないことが続くと、エージェントも人間ですし、本当に採用する気持ちがあるのか疑問に思われたりします。求人内容だけでなく姿勢やしぐさを見る傾向や、話好き、話下手、必ず実施する質問など、面接官の癖などもシェアしておくとスムーズに進捗が進むので、エージェントも安心感し、紹介がしやすくなります。
5.エージェントと目標を共有することは、とても大事です。いつまでに、どのポジションを、何名採用という採用人数目標、そしてスケジュール目標を決めます。
たとえば、「今月中に紹介してくれたら3週間で結果を出せるよう社内調整するので、来月には決まります。なので、今月中にターゲットを〇名紹介ください。紹介後の後工程で社内調整は何とかするので、来月中に◎名決めましょう。」といった形で具体的に期日と数字を決めます。具体的に決めることで、採用への熱意も伝わり、他社求人よりも優先度を上げてもらえる可能性があがります。
また、エージェントも大手をはじめ企業側担当と求職者側担当が分かれているケースも多い(以下の図②のように)ので、企業ニーズをしっかりと求職者側担当に伝えてもらい求職者へ情報を届けてもらうよう①~④までの情報とスケジュール目標はしっかりと伝わることで求職者へも伝わりやすくなると思います。私の場合は、CA(求職者担当)に同席や、CA向けの説明会をお願いし、直接情報をお伝えできるように働きかけしています。
図2 エージェントリボン図②
エージェントは後課金ではありますが、依頼があるすべての求人を充足させることは求職者の集客状況にもよるため難しく、決めたい(決めやすい、費用が高い、想いがある 等)ものを優先度高く仕事をします。なので、ターゲットの求職者がエージェントに登録にきたときも、ビジネスなので当然だとは思いますが、エージェントにとって条件がいい企業を優先したりすることもあるそうです。そのため、自社を優先してもらうためには、エージェントにとって決めたい会社だと思ってもらえることが大事です。
もちろんここに書いたことがすべてではないと思うのですが、エージェントとのリレーションシップで大事なのは、エージェントの得意分野を把握し、「できるだけ情報をオープンにすること」と「目標を明確化すること」でリレーションシップを構築することだと思います。お互いに同じ目標に向かって一緒に並走するチームのような関係性が構築できれば、採用だけでなく様々な他社事例など有益な情報を共有してもらえる等、人事の強力なサポーターになってくれると思います。