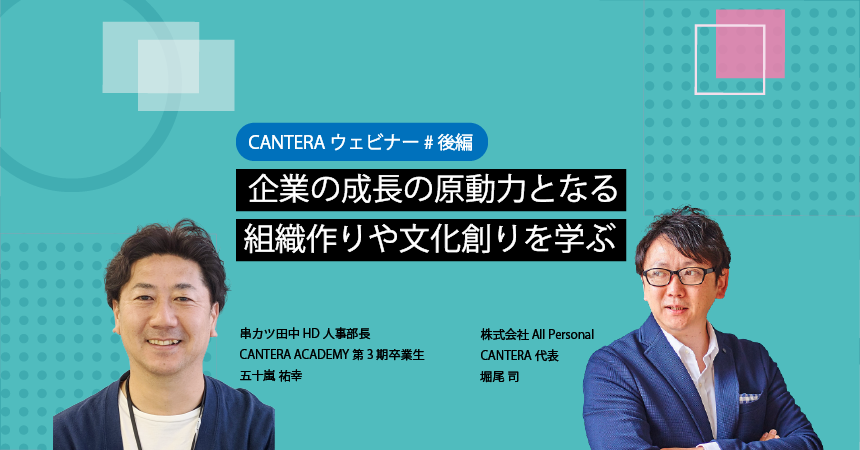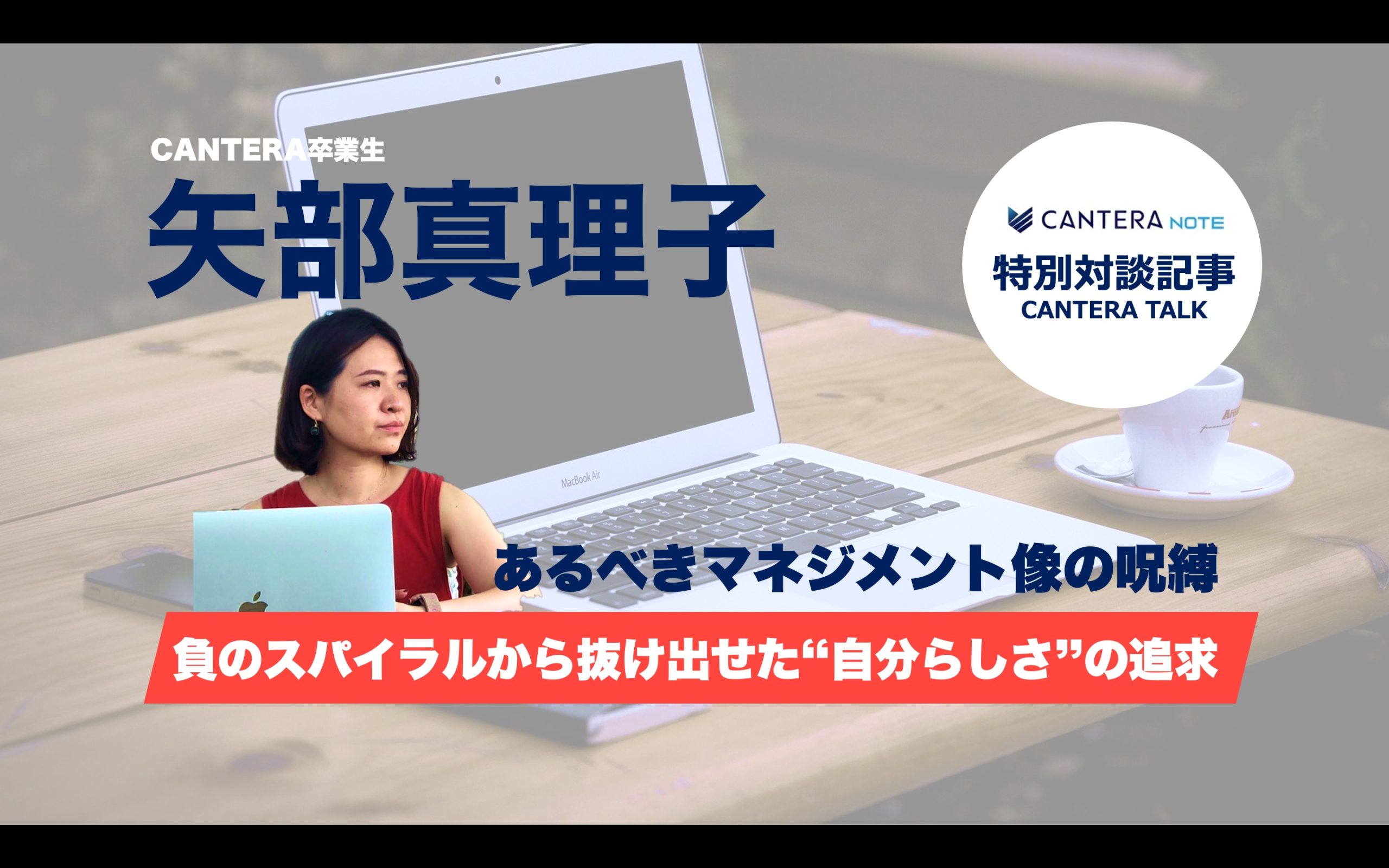デジタル時代の今だからこそ大切にしたいコミュニケーションのあり方とは?


そもそもコミュニケーションとは?
そもそもコミュニケーションとは何でしょうか?
皆さんはコミュニケーションについて問われましたら何と答えますか?
現在、出社をベースにした働き方からリモートや在宅勤務へ移行された企業も多いと思います。リモート下における上司と部下、同僚同士のコミュニケーションの量が減ってしまっているというお悩みをよく聞きます。
例えば「AさんとBさんはよくコミュニケーションが取れている」といったフレーズはよく社内で出ると思います。
しかしそれは具体的にどのような状態を指すのでしょうか?
AさんとBさんとの会話の頻度でしょうか?
片方の意思がもう片方に伝わっているかの理解度でしょうか?
どのような形式でコミュニケーションを行ったかでしょうか?
これらの定義があいまいだと本当に「今」必要な施策が何かを明確にすることは難しいかもしれません。
コミュニケーションを辞書で調べると「社会生活を営む人間の間に行われる知覚・感情・思考の伝達」と書かれています。
「知覚・感情・思考の伝達」、つまりコミュニケーションは言葉だけではないということが見て取れると思います。皆様は「メラビアンの法則」をご存知でしょうか?
①視覚情報:55% ②聴覚情報:38% ③言語情報:7%
言語情報は、たったの7%程度しか相手に影響を与えていない可能性があるのです。意外ですよね。
一見、この情報は今回のDX(Digital transformation)や働き方の変化というテーマと関係ないように思われるかもしれませんが、そうではありません。
例えば現在大きく普及したオンライン会議。果たして皆様は、ご自身が相手にどう映っているか、どう見られているかを把握できていますでしょうか?
画面とカメラの位置から焦点が合わないことは仕方ありませんが、どのような態勢・表情で会議に参加していますか?そしてその態度は会議参加者にどのようなメッセージを与えているか、まで把握していますでしょうか?
デジタルツールの活用によってあらゆるものが便利になったとしても、そもそも相手と信頼関係を築けるようなコミュニケーションが普段から取れていないと、物事が進まないのは昔も今もこれからも変わらないと感じています。
さて、先程コミュニケーションの定義には「伝達」とありましたが、伝達以外にもコミュニケーションには様々な目的が内包されています。
「誰と」コミュニケーションを取るのかを考えた時、コミュニケーションの対象は他の誰かか、自分のいずれかだと思います。

意外にも軽視されがちなのが、自分との対話です。誤解を招かないよう注意してお話します。
自分と他の誰かとのコミュニケーションはデジタルツールにより大幅に効率化されました。
SNSの発達、オンライン会議ツール、チャットツールなどです。
加えて最近では表情や声の揺らぎから、感情を予測するAIを搭載したツールまで出てきています。
一方で自分との対話は可視化されません。
にも拘わらず、今のように就業観そのものや働く環境が激変している世の中においては、自分自身「どうありたいか?」を主体的に考え、自律的にキャリアを描くことの重要性が高まっていますよね。
人は一日に1,000回以上も自らに質問を投げかけていると言われます。もしこの質問がネガティブなものだったらどうなってしまうでしょうか?
そうした自分自身との対話(セルフトーク)も立派な1on1であります。
ですのでセルフトークを自己のより良い行動変容を導くものとするのならば一例として、部下のセルフトークの傾向を上司が普段からの関わりを通じて把握し、フィードバックすることで部下の中で気づきが生まれるような環境を構築する、といったことが大切なのかもしれません。
ここまでコミュニケーションそのものについてお話してきましたが、これまでの話も踏まえてコミュニケーションの本質とは何でしょうか?
それは「伝わったことが伝えたこと」ということです。
「私はあなたに伝えたはずだ。わかっていないあなたが悪い」ではなく、自分が伝えたい意図が相手に伝わっていなければそれは適切なコミュニケーションが取れていない、ということ。
誰に対しても、自分が伝えたいように相手にも伝わるコミュニケーションができる人こそ真にコミュニケーション能力が高い人であり、ただ単にオープンマインドな人でも、話すのが得意な人でもありません。
いかがでしょうか。もし自分のコミュニケーション能力に伸び代があるとすればそれは何ですか?
なぜ、今「コミュニケーション」なのか?
では続いて「なぜ、今コミュニケーションなのか?」についてお話したいと思います。

ここ数年、AIブームが再来し、デジタル技術が著しく進歩を遂げました。それに応じて第四次産業革命やDXといったキーワードが世界中を圧巻しています。デジタルツールの発展によって、私たちはいつでも、どこでも、誰とでも繋がれる時代になりました。
そしてチャットツールの台頭や職位関係なく均等な大きさでの人物表示、ランダムな配置が為されるオンライン会議ツールの普及に伴い、コミュニケーションがよりフラットになりつつあります。
加えて、2020年は新型コロナウイルスの影響によっても大きな変化を迎えることになりました。リモート・在宅勤務に完全移行した企業様も多いのではないでしょうか?そうした働き方のシフトが起こっている今、
1.物理的に離れている中でどうすれば組織をマネジメントできるのか?
2.どのようにして社員をモチベートするのか? メンタルケアはどうするのか?
3.オフィスは本当に必要なのか?
そういった問いが話題の中心になっていますよね。これまでの常識を疑わざるを得なくなった、これが一番しっくりくる表現ではないかと思います。
私たちが所属している企業・組織は、今改めて存在意義を問われてます。皆様の会社の社員はどのような使命を感じているでしょうか?会社の想いは伝わっていますか?
実際、こちらのような調査結果があります。

リモートワークによって確実に私たちの会社への帰属意識や働くことに対する感じ方が変わっていることがわかります。働き方の変化も含め環境変化は何かしらの影響を必ず与えます。
こういった影響を踏まえて、会社としてどういった対策を取るのか、本質的な問題はなにか?という問いをいかに徹底的に考え抜くかが必要になっているのかもしれません。
出社を前提とされていた企業からすれば、リモートワークへの移行によって、明らかにコミュニケーションの頻度は少なくなっていると思います。
いかに「雑談の時間を設けるか?」という手法の話から入るのではなく、環境変化によって私たちはどういったメリット・デメリットを得ているのか、本質的な悩みは何か?それを解決するためにはどのようなアプローチを展開すべきか?そういった流れで根本的な課題から考えていきたいですね。
長い目でみれば、改めてこの軸となる存在意義を言語化して伝えられるかどうかが、社員を繋ぎとめられるかに関わってくるのではないでしょうか。
こうした環境変化の中で生き残るためには、これまでにない様々な意思決定が必要になります。皆様もこの数か月、数々の悩みにぶち当たりながら、意思決定されてきたのではないでしょうか?その意思決定の時に大切になるのが企業・組織・個人としての「あり方」だと思っています。

あり方とはつまり、倫理観、アイデンティティ、目的意識等です。
日々目まぐるしく押しよせる問題と、それに対処しなければならないというプレッシャーの中、私たちは意思決定をしなければいけません。
そのような時々に、皆様はどのような基準で意思決定をしていますか?
一つの意思決定で社員に大きなメッセージを与えることもあります。例えば成果主義への移行もその一つかもしれません。
何かを決めるということは、何かを発信するということであり、それによってどんなメッセージが発されるのかを考えていくことが大切です。とはいってもそんな余裕なんてないよ!と思うかもしれませんね。
だからこそ今の内に未来に向けて「何を変え、何を変えるべきではないのか?」を明確にすべきではないでしょうか。
Howの罠を防ぐ
何を変え、何を変えるべきではないのか?
これが定まれば企業として、組織として、個人としての軸も定まります。一番重要なのはその軸を元に様々な意思決定をしていくことです。
一つの例えとしてDXを挙げます。DXは手段であり「目的」ではないはずです。手段と目的を勘違いすると本当に大切にしたいものを失う可能性があります。

世の中の流れに乗るということは決して他社と同じ事をすることではありません。むしろ今の環境変化を踏まえ自らが適応して生き残るために必要な事に取り組むことではないでしょうか。
Howから始めるのではなく、Whyから始める。そんなコミュニケーションが変化の時代においては益々重要になっていると感じます。
いかに適切な問いを立てられるかどうか。皆様は日頃の会話において、なぜそれをやるのか、目的は明確になっていますか?
ここまで、なぜ今だからこそコミュニケーションを見直すことが大切なのかについてお話ししてきました。
講演の後半部分を取り上げる次回は「組織を強くするコミュニケーションとは?」についてお伝えします。

筆者が登壇したイベントは以下となります。
ITトレンドEXPO2020
人事としての専門性を高めたい!とお考えの方はこちらを是非ご覧ください。
【執筆者も講師を務めています!】