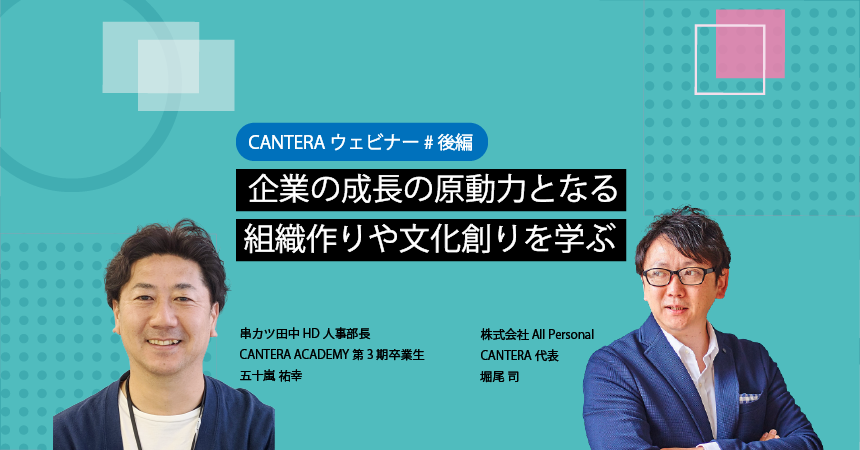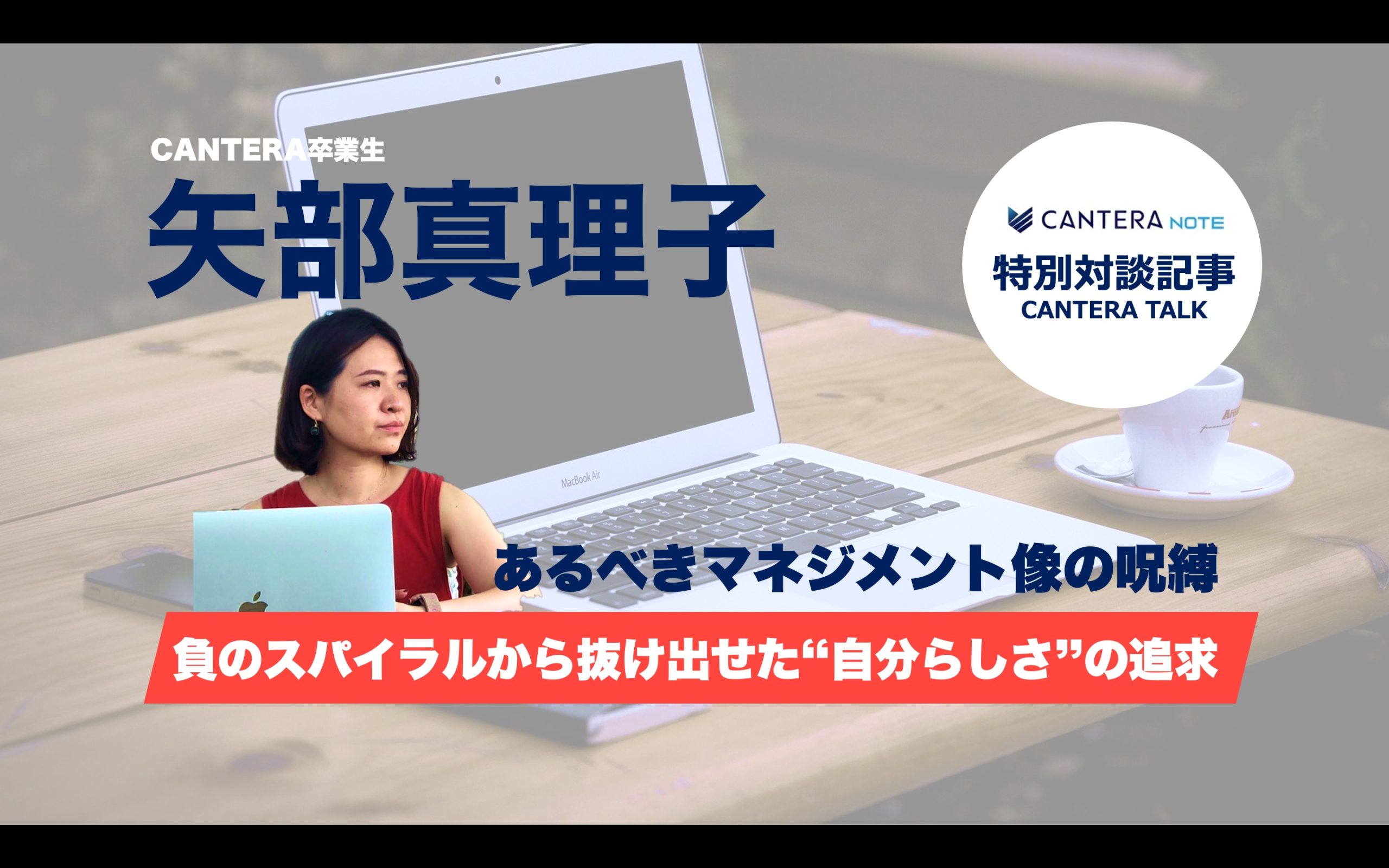コミュニケーションと向き合う事がDXを更に加速させる

※「ITトレンドEXPO2020」はこちら
※(前編)はこちら
※本稿はデジタル時代の今だからこそ大切にしたいコミュニケーションのあり方とは?(前編)からの続編内容となります。
11月末現在で新型コロナウイルスの感染拡大が更に加速し、改めてテレワークや在宅勤務へ全面移行している企業も増えているのではないでしょうか?
そんな中であっても私たちは企業人である以上、チームで協力し合い、ビジネスの成功を目指さなくてはなりません。
リアルでさえ難しいチーム作り、そんな中、オンライン中心のコミュニケーションになって苦労されている方も多いのではないでしょうか?
強い組織を作る、組織のパフォーマンスを高める、聞こえはいいですがとても難しいことですよね。
ところで皆さんは何が組織を強くすると思いますか?
事業戦略でしょうか? 組織として明確な方向性を明示することでしょうか? それとも個々の業務遂行能力や経験の豊富さでしょうか?
ここでいう「強い組織」とは、困難を協力して乗り越え、事業推進を通じて結果を出す組織、と定義したいと思います。
上記に挙げたいくつかの要素はその実現に向けていずれも重要かもしれません。
ですが、実はある前提が整っていなければ、そもそもこれらの要素は効果を発揮せず終わることになります。私はこれまで何度もそういった経験をしてきました。
その前提は何か。それは今回のテーマである「コミュニケーション」です。
組織を強くするコミュニケーションとは?
そもそも基本的に日々仕事をしている中で「よし、一旦うちの組織のコミュニケーションの在り方そのものを見直そう!」といった会話になることはあまりないと思います。
なぜならコミュニケーションに関しては以下のような捉え方をされているケースが多いからだと感じています。
・DX推進にはテクノロジー活用を通じた生産性向上が重要で、優先順位が低い
・コミュニケーションスキルは個人に起因するもので組織におけるテーマではない
・組織内に余計な負担やコストが発生する
・自分のコミュニケーション能力には問題はないはずだ
普通はこう感じますよね。とてもよくわかります。コミュニケーションは目に見えず定量効果も測りづらい、取っ付きづらいものと思われているためです。
ですが、前編に書いた通り「伝わったことが伝えたこと」がコミュニケーションの本質である中で、多くの組織課題は「組織全体に伝えたいと思って発信していることが、何かしらの問題によって正しく伝わっていない」または「伝わってはいるけど人間関係の悪化により素直に従いたくない」という状況によるものがほとんどです。
私たちは経営戦略や多くのビジネススキルを学んできた一方、土台となるコミュニケーションについては教えられることはなく、各自が自らの経験から学んでいるに過ぎません。全世界の人がコミュニケーションを通じてビジネスをしているのに、不思議なことですよね。
例えば、人は一日に1,000回以上、自らに問いを投げかけています。
この問いの質もコミュニケーション能力の一つであり、その重要性についてはアインシュタインも言及していました。

よって、今回ご紹介したい組織を強くするコミュニケーションとして、私が実践し他の方にもお勧めしているのが組織の中で「問いを中心」に議論することです。
問いを中心に議論する

見えている課題を解決するためのHowやWhatではなく、WhyやPurposeから考えようという話が昨今その重要性を見直されています。
私が問いを中心に置いて議論した方がいいと感じているのはそれに加えて、議論を通じてお互いの物事に対する捉え方を理解し合うことができるからです。
例えば「どうすればリモートでも評価の納得性を高めることができるか?」という問いに対して関係者で議論するとします。
この一つの問いに対して様々な意見が出てくると思いますが、面白いのはお互いの意見をよく聴いていると「評価の納得性」に対する各自の定義が異なっていると気づくことです。
WhatやHowといった手法から議論して中々議論が収束しないケースは、そもそも前提である各自の言葉の定義が違うまま、あたかもお互い同じものをイメージしていると思い込んで議論していることが多くなります。
例えば「リーダーシップのある人材をどう育成するか?」という議論において関係者同士で「リーダーシップ」の定義が擦りあっているか怪しいことはありませんか?
問いを中心に議論することで、お互いの目線が合ってくる。目線があえば目指したい世界のイメージも擦り合い、結果的に取り組むべきことも明確になって議論がまとまる。
そんな流れができてくるはずです。
「問いを中心」に置いて議論することに加え、もう一つ大切なのは「場の見立て」をすることです。
場の見立て
あらゆる議論の場にはファシリテーターがいますよね。人事はその役割を担うことも多いのではないでしょうか?
関係者を集め、いきなり議論を始めたくなるものですが、その場に集まった関係者の心中はどうなっているのか、場の空気はどうか、そういった「場の見立て」が実はその後の議論の質を大きく左右します。
皆さんも次のような経験はありませんか?
頭では理解できるけど、感情がついてこない。何となく真面目に真正面から議論したくない、意見したくない。気に食わない…
ここまでいかずとも、関係者一人ひとり、議論の場に集まった時の心の状態は大きく異なります。
プロである以上、心の状態なんて関係ない、ただ必要なことを議論して答えを出すのみだ。という方もいるかもしれませんね。私もそう思いたいです…。
ただ、人間である以上、白か黒かといった割り切りができるケースは稀で、グレーであることがほとんど。
ですので議論を通じて答えを出すだけでなく、その後も関係者同士が鮮やかな連携を通じて互いを信頼し合い、高いパフォーマンスを発揮することを目指すのであれば「場の見立て」が必要になると思います。

仮に私が問いを参加者に投げかけたにも関わらず、「(シーン…)」と特段の反応もない場合は、参加者に対して、
「話しづらいテーマでしたか? どういった点に話しづらさを感じますか?」
「意見が出てきませんでしたが、今何を感じていますか?/考えていますか?」
「そもそもこの場に対して腹落ちされていないようにも感じますが、どのような点にそれを感じますか?」
といった投げかけをしていきます。
言葉に出なくても、よく場と参加者の様子を観察すれば、どこかにエネルギーが溜まっている(大体が不満や困惑)のが見えてくるものです。
そのエネルギーの中身を取り上げて参加者に問いかけることで、自然とエネルギーが漏れ出すように参加者から意見が出てきます。
そんなことをやっていてはいつまで経っても本題に入らないじゃないか。呑気に議論している場合じゃないんだ。
そんなツッコミが聞こえてきそうです(笑)
確かにそうかもしれません。ただ、議論を通じて成し遂げたいことは問題に対する対処法や目標を達成するための取り組み方針を明確にすることではなく、明確化されたものを実践し実際に成功に繋げることなはずです。
場合によっては時間がかかるかもしれませんが、もし本当に組織を強くしたいのであれば、ここは時間をかけてでも参加者同士の目線合わせや腹落ち度を高めておかないと、議論の答えが出てもお互いに心から連携しようと思えず、どこかで歪みが生じてうまく行かなくなります。
(もちろん、緊急対応が必要な状況下では即座に意思決定し、参加者の納得度に関わらず実行する強い統率力は必要です)
もし、場の見立てが苦手だなと感じた方はあなたの組織や議論の場に隠れている「暗黙の了解」がないかを探してみてください。

参加者同士の目線合わせはできて、議論するために中心に置くべき問いも明確になった。それなのになぜか議論が進まない…
そんな時には「暗黙の了解」が原因であることが多いです。
もしこのような「暗黙の了解」がある場合は、それ自体を議論の場に挙げてしまうという方法があります。
「私たちの組織って何となく上の役職者の方よりも先に発言してはならないって空気感があったりませんか? それって私たちが今回本当に目指したい姿を実現するために、この場においても本当にそうでなければならないのでしょうか?」
「今回の場では役職関係なくランダムで話をしていきましょう。〇〇さん(役職者でない)、今回のテーマに対してどのようにすればうまくいくと思いますか?」
例えば、それぞれの立場の参加者に配慮しつつこのような投げ掛けをすることで少しずつ議論の場が「暗黙の了解」から解放され、活発な議論が交わされるようになります。表現の仕方は各自の組織風土や関係者との関係性によって変えます。
いきなり議論の場で実践するにはハードルが高い場合は、事前に参加予定者に個別に話を聞き、設定している議論の場に対してどんなことを感じているかを聴いておくという手段もあります。
このように「問いを中心」において議論し、「場の見立て」を通じて参加者の心の状態を議論できる状態に整えることで、議論が終わった後も高いパフォーマンスを維持できるような「組織を強くする」コミュニケーションを実現することができると考えています。
また、適切な問いさえ設定できれば、事業戦略と施策の方向性の一貫性も出てくるため、会社全体の成長にも繋がるはずです。
たかがコミュニケーション。されどコミュニケーション。
いかがでしたでしょうか?
日頃私たち誰もが呼吸をするくらい気軽に誰かとコミュニケーションをとっています。一方で、互いに、そして自分自身と良好な関係を築き、パフォーマンスを高めるためのコミュニケーションは「スキル」であり意識しなければできません。
たかがコミュニケーション。されどコミュニケーション。
制度を変えたり新しいツールを入れる前に、今あなたの組織で行われているコミュニケーションの状態は、理想を10とするとどれくらいでしょうか?
加えて、あなた自身の周囲に対する関わり方はどうでしょうか?
個人が共通の目標達成(結果を出す)のために集まり組成される集団が組織です。
だからこそ、目標達成の確実性を上げるコミュニケーションの在り方を見直してみませんか?
急がば回れ、もしかすると大きな変化が待っているかもしれません。
さいごに〜能登さんにとっての2020年を総括すると?〜
新型コロナウイルスの感染拡大により2020年は全く想像していなかった展開を迎え、そして先行きが不明確なまま終わりを迎えることになりました。
「危機」とは「危険」と「好機」だという人がいました。まさにこの変化をどう捉え、来年に向けて何を変えて何を変えないのか、じっくり考えたいと思います。
皆様は来年、何に一番力を入れて取り組みたいですか?
人事としての専門性を高めたい!とお考えの方はこちらを是非ご覧ください。
【執筆者も講師を務めています!】