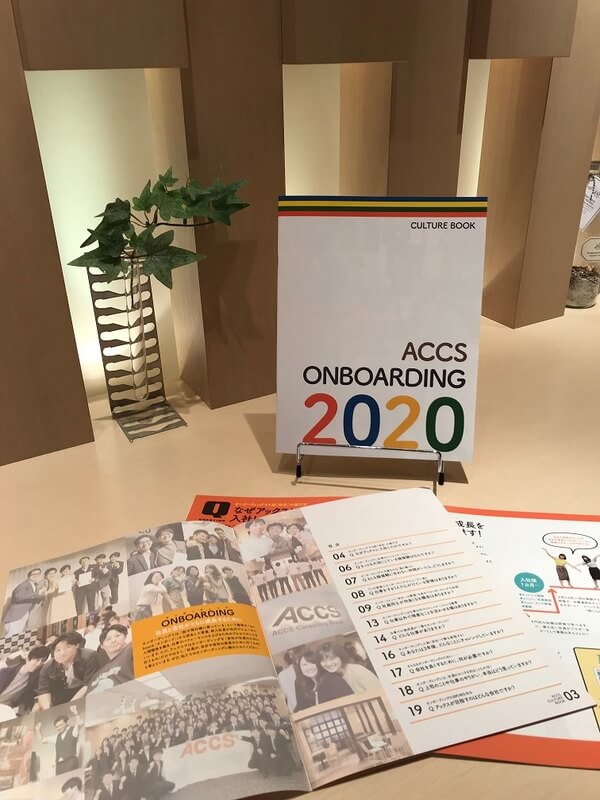自ら転職して身にしみた「オンボーディングの重要性」

フルオンラインのオンボーディングで感じた4つの問題
1.顔と名前が覚えられない問題
Zoomなどのテレビ会議ツールでのやりとりでは画面上に顔と名前が表示されますし、タレマネシステムも社内に公開されているので、顔写真付きで名前も部署もプロフィールもわかります。
にもかかわらず、なかなか顔と名前が覚えられないのです。スマホやPCを使っていると漢字が書けなくなるのと同じようなことかもしれません。
2.誰に何を聞いたらいいのか&こんなこと聞いてもいいのか問題
それぞれ何を担当しているのかが分かる担当者の一覧表は公開されていますし、チャットツールで気軽に質問できる環境もあります。
「わからないことがあったら気軽に聞いてね」と言ってくれる上司も同僚もいますし、定期的な1on1も実施してもらっています。もちろん40歳を超えたおじさんですから、仕事を進めるために必要なことは適切な人を見つけて質問しています。
それでも「こんなこと、わざわざチャットで聞くのもなぁ」「今度出社したときにまとめて聞けばいいか」と感じることは何度もありました。テレビ会議やチャットでは再現できない、オフラインならではの間とか空気感みたいなものが作用しているのでしょうか。
3.隣の人が何をやっているのかわからない問題
前述したとおり、情報としては誰が何をやっているかはわかりますし、スケジュールも公開されています。
にもかかわらず、みんながリモートで働いていると、姿が見えないので実感が持てないのです。毎朝オンライン朝礼で顔を合わせたり、チャットで雑談したりしているけど、「何をしているのかわからない」気がするのです。
この問題は、普通に出社しているときでもよく耳にする課題感ですが、リモートワークで「わからない気がする」症状がさらに悪化してしまっているのだと思います。
4.自分の居場所があるのか不安になる問題
当然ですがミッションやタスク、期待役割は与えられています。中途入社ですから、入社する数ヶ月前からその内容は理解して入社しています。
ところが、自宅で画面に向かって仕事をする日々が続くと「誰の、何のためにやっている仕事だっけ?」と、仕事の意義や目的を見失いそうになる瞬間があるのです。
他者に貢献できているという手応えを感じると「自分はここにいてもいいんだ。必要とされているんだ」という自己効力感が湧いてくるものです。
コロナ禍のこの1年間、メンタル不調となる新入社員が激増している話はメディアや他社の人事の方を通して何度も耳にしました。きっと自己効力感や自己肯定感がメンタル疾患に大きく影響しているのでしょう。この問題のリアルさを感じざるを得なかった1ヶ月間でした。
問題解消には「ゆるめの時間」が必要
ここまでお読みいただいて、何か気がついたことはありましたでしょうか?
今回、私が感じた4つの問題は短期的・直接的には業務のパフォーマンスに影響しにくい内容が多いのです。しかしながら、これらが積み重なってくると、生活習慣病のように社員や組織の健康状態にじわじわとダメージを与えてくるような気がします。
そして、こういった一見緊急度が高くなさそうな問題の多くは、コロナ以前の環境ではオンとオフの中間にある「ゆるめの時間」によって解消されていたのではないでしょうか。
(ゆるめの時間の例)
・ランチタイムや、お茶をしながらの雑談の時間
・コピーついでの立ち話の時間
・客先の行き帰りの移動時間や会議前後などのすきま時間
・業務後の飲みニケーションの時間
働き方が、コロナ前の状況に戻ることはないという前提の中で、社員と組織のパフォーマンスを上げていくために、
・オフラインのフィジカルな場で「ゆるめの時間」を意図的につくる
・オンラインでツールなどを駆使して「ゆるめの時間」を再現する
といったアプローチを考えていくことを、私のミッションに追加することにしました。
今回はオンボーディングで感じた問題として取り上げましたが、オンライン下で働く誰もが抱える問題でしょう。目新しい情報はあまりなかったかもしれませんが、当事者としての体験記が皆様のヒントになれば幸いです。