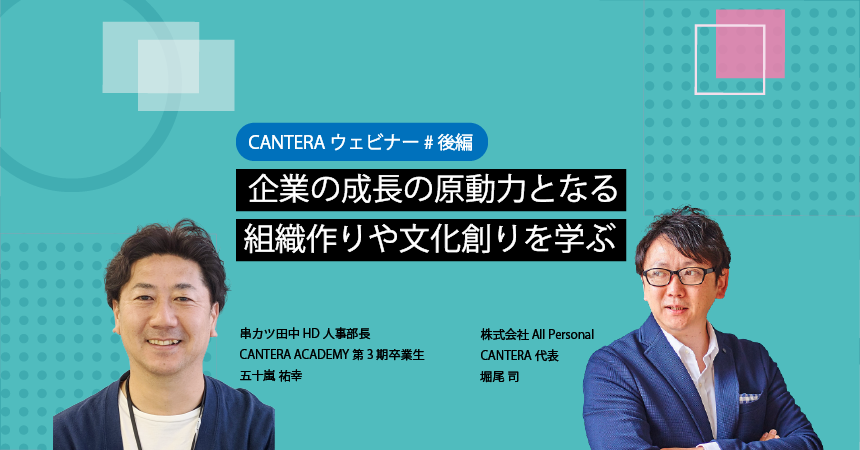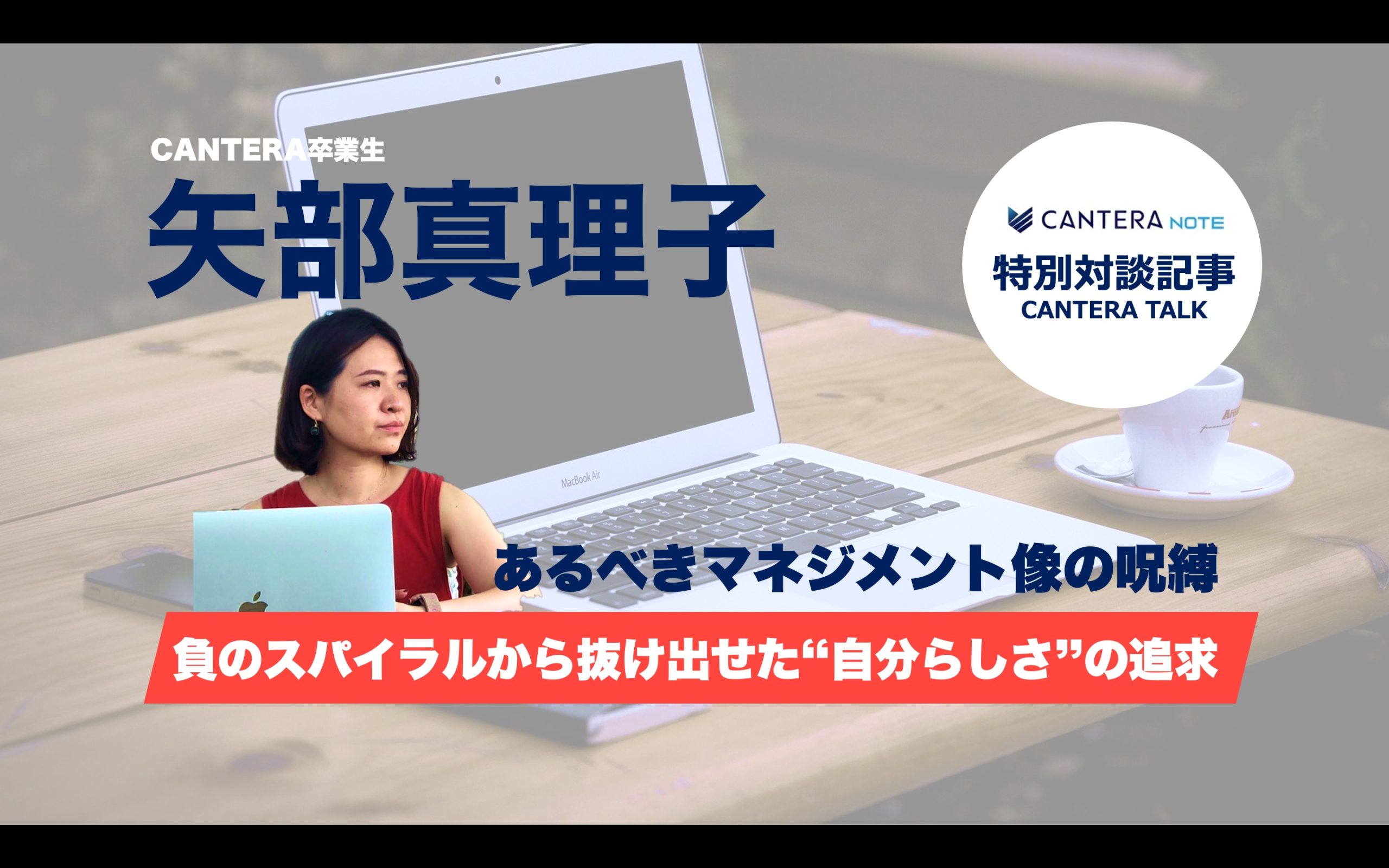マネジメントが向いてないと思った私が、チームを激変させた4つのアプローチ法

中途採用責任者として年間100名以上の採用をするべく、メンバー10名と共に走ってきた3年間。責任者になった当初は、マネジメント向いてないと悩む日々を過ごしていましたが、ある取り組みをしてからチームの雰囲気が変わり、結果的に少数精鋭で最大な結果を出せるチームへと変貌を遂げました。
現在、マネジメントに苦戦されている方やこれからマネジメント職に就かれる方の何か気づきとなれば嬉しいです。
できないことをできるようにするスタイルからの脱却と、
出来ることをとことん追求できるチームの業務振り分け
マネジメントを始めた最初の頃は、少数精鋭のチームだったこともあり、全員がある一定の基準まではできるようにならないと仕事が回らないと思い込んでいました。メンバーのできていないところ(=私が期待しているところまで達しない点)を見つけては、どうやったらできるようになるのかをミーティングや1on1で話し合っていました。当時26歳の私は、できることが増えたらメンバー自身が仕事がしやすくなると思っていましたし、成長の機会提供につながると考えていたのです。
が、現実はメンバーからの不満の声の嵐。その声を受け取る余裕が自分になく、しかもこの状況で成果を出さなければならなかったので、メンバーに依頼するのをやめ、できることは自分でする、という仕事を抱え込む悪循環になりました。
1人ではどうにもならない業務量と向き合っていたあるとき、ふと、リーダーになって実現したかった世界を思い出してみたのです。
私は、苦しむためにリーダーをやっているのではなく「メンバーも自分自身も楽しく仕事ができる状態を作るためにリーダーになりたかった」のではないかと。
そこから、どうやったら楽しく仕事ができるのかを改めて考え直しました。その結果、「できないことをできるようにするために時間を割くのではなく、まずはできることでチームのために貢献できる実感を味わうこと」「メンバーから承認される感覚を得られる環境を整えること」これが必要不可欠だと気がついたのです。
そこから、各メンバーの業務範囲と役割を抜本的に変え、なかったポジションは新たなつくるなど、苦手なことよりも得意なことにフォーカスできるチームの方針を掲げて動くようにしました。
自分の余白をとにかく生み出す
しかし、新しいポジションやチームの中での業務分担を考えるのは容易ではありませんでした。自分自身のスケジュールがパツパツだったのもあり、メンバーの得意不得意を知る時間がほぼなかったからです。
もちろん、得意なことや好きなことをメンバー一人ひとりにヒアリングしていきます。ただ、本人が当たり前にできてしまっている中に得意なことや強みは隠れているので、ヒアリングだけでは見えてこないことも少なくありません。その部分を見つけて、業務に生かしていくためには自分の時間的余白を設けて、一緒にプロジェクトに入る機会や雑談をする時間を意図的に設ける必要があると思いました。ミーティングの短縮化や業務のやるやらないを明確にして、自身のタスクを削ぎ落とすことをして時間を生み出したのです。
すると、メンバー1人ひとりのことがよく見えるようになりました。例えば「自分には強みがない」と言っていたあるメンバーの場合。実はいろんな方々の置かれている状況に目線を合わせて話を聞くことができ、一人ひとりにあった形でわかりやすくレクチャーできるという強みがあるということを見いだすことができたのです。
彼女の強みを活かせるように、教育担当というポジションを設けることにしました。彼女自身も自分の強みを活かして、無理なく楽しくチームへの貢献実感を得られるようになったのです。育成プランやチームの改善ポイントなどをどんどん提案してくれるようになり、ものすごい勢いでチームの雰囲気やスキルが向上しました。
学習スタイルの違いを理解し、1on1の仕方を変更
自分の時間が生み出せてようやく、一人ひとりと向き合うことができ始めた頃、『ドラゴン桜とFFS理論が教えてくれる あなたが伸びる学び型』を読んで人には学習スタイルの違いあることを知りました。トライ&エラーしながら学習していくタイプと、段取りを決めて着実にステップアップしていきたいタイプの2種類の学習タイプがいるということです。
すごく簡単にお伝えすると
・トライ&エラーのタイプ(拡散型)
目的や目標を共有すれば勝手に行動します。むしろ、ルールやマニュアルが多ければ多いほどストレスを感じ行動できなくなります。自由さが重要です。
・段取りを決めて行動するタイプ(保全型)
目的・目標達成までのマイルストーンが見えれば着実に行動し、より良いものにブラッシュアップしていくことが得意なタイプです。目的の共有だけされると何をどうしていいのかわからなくなり、それがストレスとして働きます。
この違いを理解した上で、トライ&エラータイプは、目的と納期の合意が取れたら、1on1は月1回程度の実施にしました。かつ、1on1の内容はほぼ雑談でその時メンバーが話したいことを聞くというスタンスを徹底したのです。
一方で、段取りを決めて行動するタイプは、週次で1on1を設定し、細かく業務の進み具合やそこで困っていることなどをヒアリングする時間に重きを置きました。
これをし始めてから、メンバーが思っていることや不安に感じていることがわかるようになり、何を解決するとみんなが心地よく働けるのかがわかるようになったため、チームとして機能するようになったのです。
1日メンバー全員に1回以上ありがとうを伝え続ける
メンバーに感謝を伝えること。これは当たり前のことかもしれないですが、一番即効性のある具体的な行動です。
伝えるポイントは大きく2つ。存在承認と行動承認です。
・存在承認
その人の存在自体を受け入れて言葉にすること。
例)「●●さんがいてくれるだけでチームが明るくなるよ〜!ありがとう!」
・行動承認
行動してくれたことに対して言葉にすること。
例)「●●さんのこのプレゼン資料めっちゃ内容網羅されていて、伝えたいポイントがわかりやすくてお願いしてよかった!さすが!ありがとう!」
ちなみに、信頼関係がいまいち築けていないな〜という場合は、存在承認の方を重視した方が効果的です。人は心理的安全性が担保されていると思えないと、どれだけ行動を承認されても「なんでこの人私のことわからないのに褒めてくるの?」と懐疑的になります。これはコーチングの勉強をしていることで学んだポイントなので、皆さんもぜひ活用してみてください。
私が実践してきたことはすぐに行動に移せる部分が多いかと思います。マネジメントで悩んでいる方は、ぜひトライしてみてください!