労務未経験だった私が、労務を効率化するために取り組んだ3つのこと
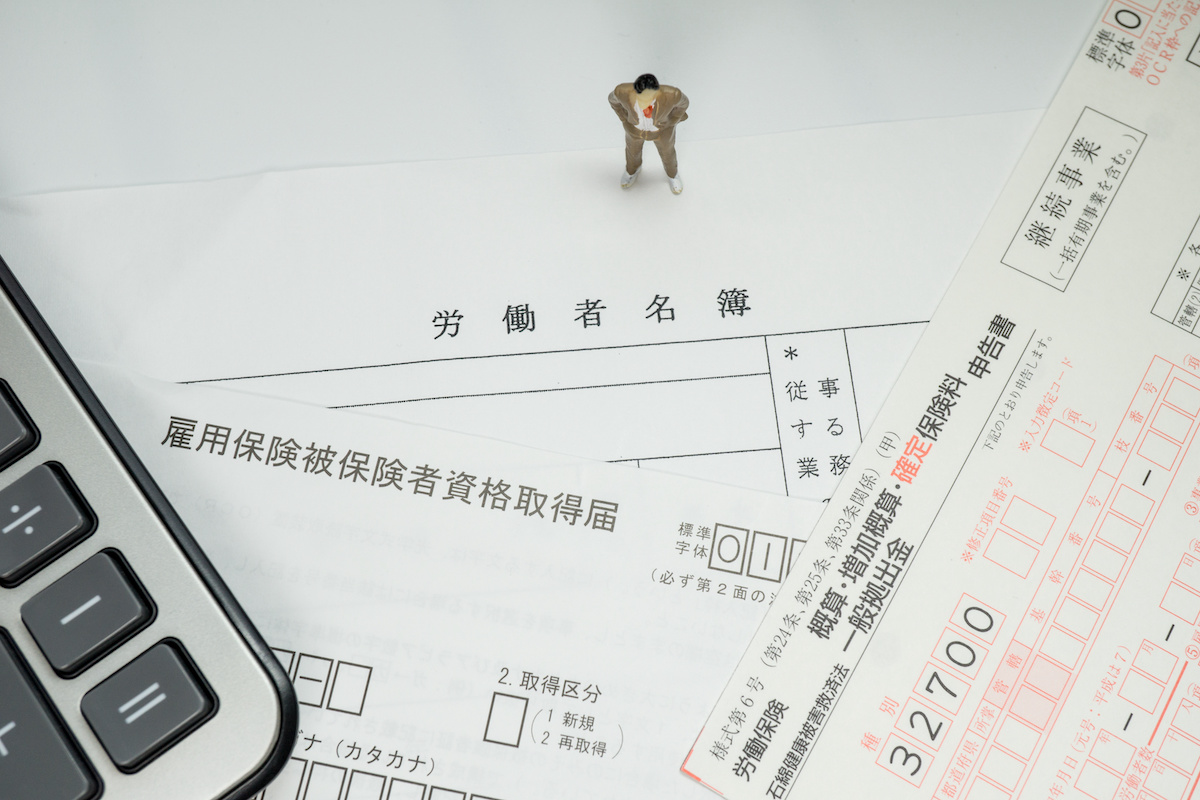
私は、人材エージェントから人事へ転身しました。当初は採用業務をメインにやっていたのですが、急に労務を担当することになったのです。
しかし、実務経験は未経験でした。そんな労務未経験だった私が、労務を担当してから考えたことと取り組んだことを書いてみようと思います。
まずは労務の仕事を調べてみた
そもそも労務の仕事を理解できていなかった私は、まず労務の仕事は何をするのか調べました。
1:勤怠管理
従業員の就業状況を雇用主が正しく把握し、管理すること。就業状況とは、日々の出退勤時間や休憩時間、時間外労働時間や出勤日数、欠勤日数、有給休暇の取得日数など。
過労死などが問題化されていることもあり、厚生労働省は労働時間の削減を推進しています。労務担当者は36協定に限らず、比較的高頻度で改正される労働基準法を理解しておく必要があります。
2:給与計算
勤怠情報などをもとに従業員に対して支払う給与の金額を算出する業務。基本給や諸手当だけではなく、控除項目の算出も行います。同時に、社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税といった国に納める保険料、税額の計算もします。このときに月変という社会保険料が変更になる場合もあり、単月の算出だけでなく複数月を確認する必要もあります。
正社員や契約社員、アルバイト・パートなど、雇用契約に応じて異なるルールが適用されるため、慎重に正確な作業が求められます。
3:社会保険の手続き
民間企業の被雇用者は、雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険・介護保険(40歳以上)といった社会保険、労働保険に加入する必要があります。
保険の手続きができていないと、病気やけがをしたときや定年後の年金受給の際などに、従業員が不利益を被ることになります。入社時・退社時・異動・出産など変更時・労災発生時などに迅速かつ正確な手続きが必要です。
4:年末調整
給与所得者が1年間に源泉徴収された所得税などを再計算し、所得税の過不足を精算する制度。年間給与所得が2000万円を超える方や災害減免法によって所得税の徴収猶予を受けている方などの一部を除き、雇用形態にかかわらず全ての従業員が対象となります。
書類の配布、従業員への説明、質問回答、書類の回収、内容のチェック、所得税の還付あるいは追加徴収まで担当します。毎年の定例業務ですが作業量はかなり多いです。
5:福利厚生
福利厚生にかかる費用は、社会保険料の企業負担分である法定福利費と法定外福利費に分類されます。
法定外福利費は社宅の提供や育児支援、慶弔金の支出などが挙げられます。ただし、会社の状態や従業員の多様なニーズから変化させる必要があり、定期的に見直し・改善を行います。
6:人事関連規程管理
就業規則や人事規程は、会社という組織に属するすべての者が遵守しなければならないルールです。必ず定めなければならない事項として、労働基準法など法令にも関わります。
明文化されている規程は企業によって異なります。よくみるのは人事評価規程、育児介護休業規程、出張旅費規程、慶弔見舞金規程などだったりしますが、社会の変化や社内の変化もあり適切なタイミングで適切な改訂を行うことが必要です。
7:安全衛生管理
企業は、労働安全衛生法をはじめとした法令を遵守するのはもちろんのこと、従業員の安全と健康保全のため、医師による健康診断を行なわなければなりません。
健康診断は、従業員を雇い入れる際だけでなく、年1回以上定期的に行う必要があります。結果の記録、従業員への通知、必要な者への保健指導、労働基準監督署長への報告なども必要です。
また、月1回の衛生委員会の運営、常用雇用者が50人以上の事業者に対して義務化されている職業性ストレスチェックの実施も必要です。ストレスチェックの導入や産業医との面談フローなども、労務の重要な役割です。
労務未経験だった私が行ったこと
私は労務未経験なだけでなく、慎重・正確な作業などが苦手なので、最初はかなり不安でした。その中で、確実に労務の業務を進めるために行った3つのことをご紹介します。
1.法律や業務の知識
労働三法、厚生労働省のページ、法改正情報をチェック、あとははじめての人事みたいな本を複数読みました。正直、それまで学んだことがなかったので、最初は壁を感じましたが、やるしかないと腹決めをして取り組みました。
知識が増えてくると、“役所へ提出する書類”が多いこと、”従業員からの書類などの回収”が負担に感じるようになりました。そのため、システム導入を検討したのです。
2.業務効率化のためのシステム導入
私はミスなく遅延なく行わないといけない業務なのに、知見が浅いだけでなく、書き損じしてしまうかもしれない書類の多さで正直面喰いました。
そのため「入退社など社保手続き」「人事管理」「勤怠管理」「給与計算」「年末調整」「ストレスチェック」についてはシステムを導入し、業務効率化を図ることにしたのです。
(1)入退社など社保手続き
とにかく労務業務に対して知見がなかったので、労務経験豊富な方が開発されたという「SmartHR」を導入しました。
これによって入社退社手続き、転居などの従業員情報の変更手続きをミスなく遅延なくできるようになり、かなり時間短縮につながったのです。社労士との連携もしやすく、個人情報のやり取りもスムーズになりました。
(2)人事管理
異動や評価履歴を含めた人事情報を一元管理できるようにシステムとして、一番可変性の高い「カオナビ」を導入しました。
ExcelやPDFなどのデータ蓄積も可能で、評価フロー設定もでき、従業員のすべてのデータを一元管理ができるようになりました。過去のタイミングでの評価や給与賞与額なども、すぐ出せるのも便利です。
(3)勤怠管理
いくつか検討した中でTeamSpiritを導入しました。
Salesforce上で動くシステムでUI/UXがよく、これまで勤怠システムを使い慣れていない方でも勤怠打刻や工数管理で使いやすいことが決め手でした。特に工数管理は後で導入すると結構めんどくさく感じてしまうと思うので、これを期に入れられることは大きかったです。
ただ、導入時設定はかなりの手間がかかりました。設定のためのキックオフ等も行っていただき、日々設定画面とにらめっこをする時間がしばらく続きました。
(4)給与計算
絶対に遅延なくミスなく行う必要があるので、ここは一番慎重に考え、アウトソースサービス等も検討しましたが、最終的には社労士へ委託をしました。
時間外手当や時給制の方がいる場合、毎月月変をチェックする必要があります。やはりプロの目を入れないと月の社会保険料を払いすぎたり、逆に不足してしまうことがあるので、労務に明るくない私にとっては労務関連のプロである社労士に委託をすることが必要不可欠でした。
(5)年末調整
手続きを誤ると社員に迷惑がかかるので、ミスなく作業を進めるためにシステム「SmartHR」を入れました。
システムで実行する前は、従業員全員が上で提出していただいていたのですが、年1回なので、書きなれた方もおらず、結構ミス率が高かったのです。
SmartHRなら従業員も入力しやすく、また自動で計算してくれるので、ミスが大幅に削減されました。そのうえでプロである社労士にチェックしてもらうことで、ミスなく期日までに進めることができました。
(6)ストレスチェック
やはりこちらも紙で実施すると、個人結果の管理や従業員からのデータ回収が進まない恐れがあったので、システム導入することにしたのです。さまざまなシステムを比較した結果、ストレスチェックの実績が豊富なHRデータラボが運営する「ストレスチェッカー」を導入しました。
実施者がいれば無料でできたのが大きな決め手でした。検査も集団分析も可能なので、とても助かりました。集団分析の考察は自分でやりましたが、これまで見えてなかったことなどを見ることもできました。
ただし、これらのシステムに頼り切ったわけではありません。労務未経験だからこそ自分の知見を深める必要もあるため、システムを使う際にも「いま何の作業をしているのか」を確認しながら作業を進めていました。
手続き関係をシステムを使わずにすべて社労士に委託するのもひとつの手ですが、それでは自分自身に知見がたまりません。費用を抑えられて業務を効率化でき、知見も蓄積できるシステムと、社労士のチェックを組み合わせるのが、労務未経験だった私にとってはベストだったと思っています。
3.社労士との関係性づくり
労務の仕事をするうえでは、ここが一番大事かもしれません。
社労士によって、労務問題が起きないように整備することが得意な方、給与計算等の事務作業が得意な方、問題が生じた際に闘える方など、それぞれ得意分野があります。自社に合う社労士に顧問になっていただき、会社の状況をよく共有しておくといいでしょう。仲良くなると、業界情報も教えていただけるので、早々に規程の変更への準備もしやすくなります。
はじめて労務担当になるとプレッシャーを感じることも多いでしょう。私もはじめはそうでした。ただ、どんな仕事であれ、自分には何の知識が足りていないのかをきちんと見極め、どうすれば漏れなく、ミスなく、遅延なく効率的に業務ができるかを考えることが大事です。そして、システムや社労士などの力にも頼りながら、自分に知見をためていくといいと思います。
はじめて労務担当になった方に少しでもご参考になれば嬉しいです。


