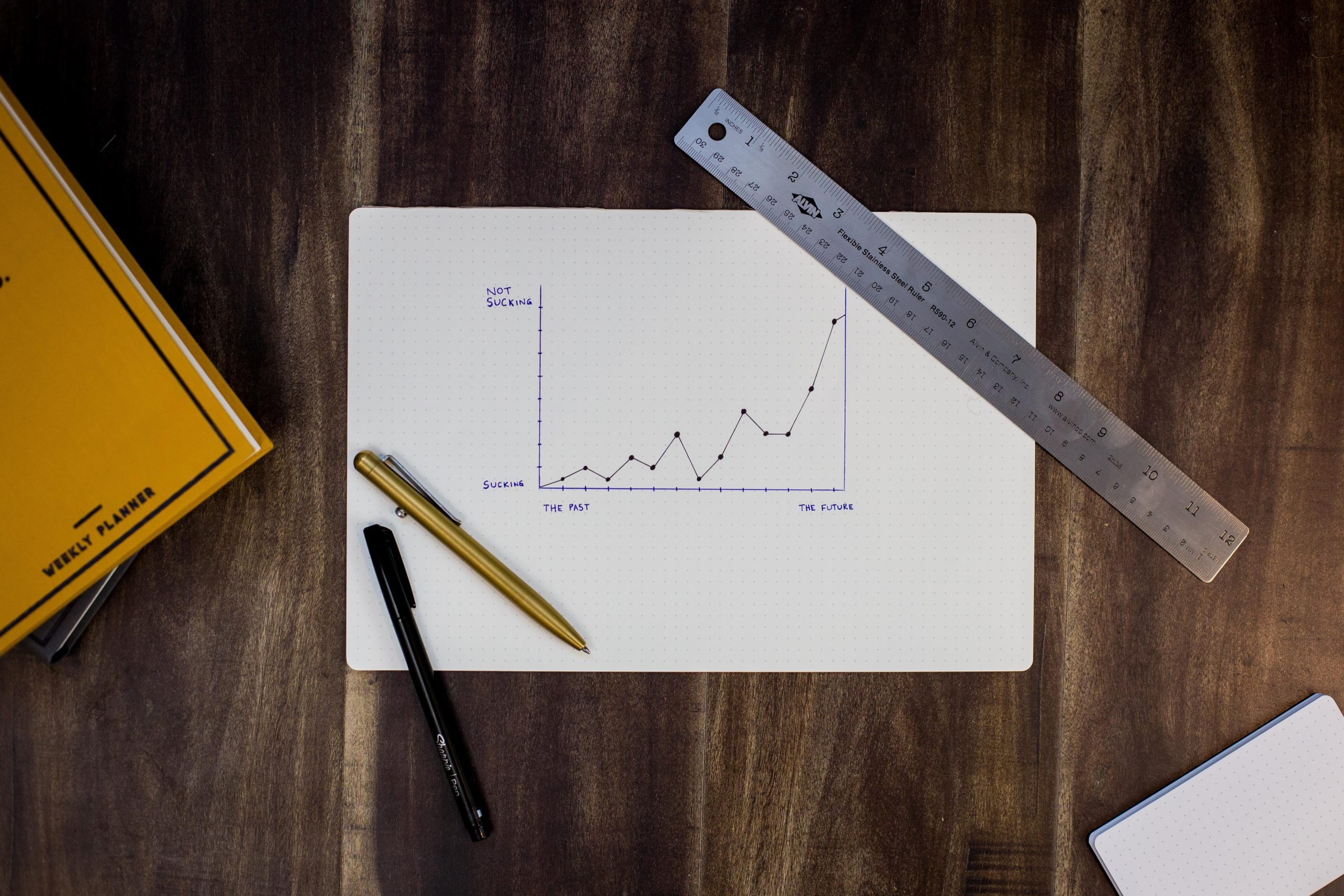「採用力の公式」から自社の採用戦略を問い直す
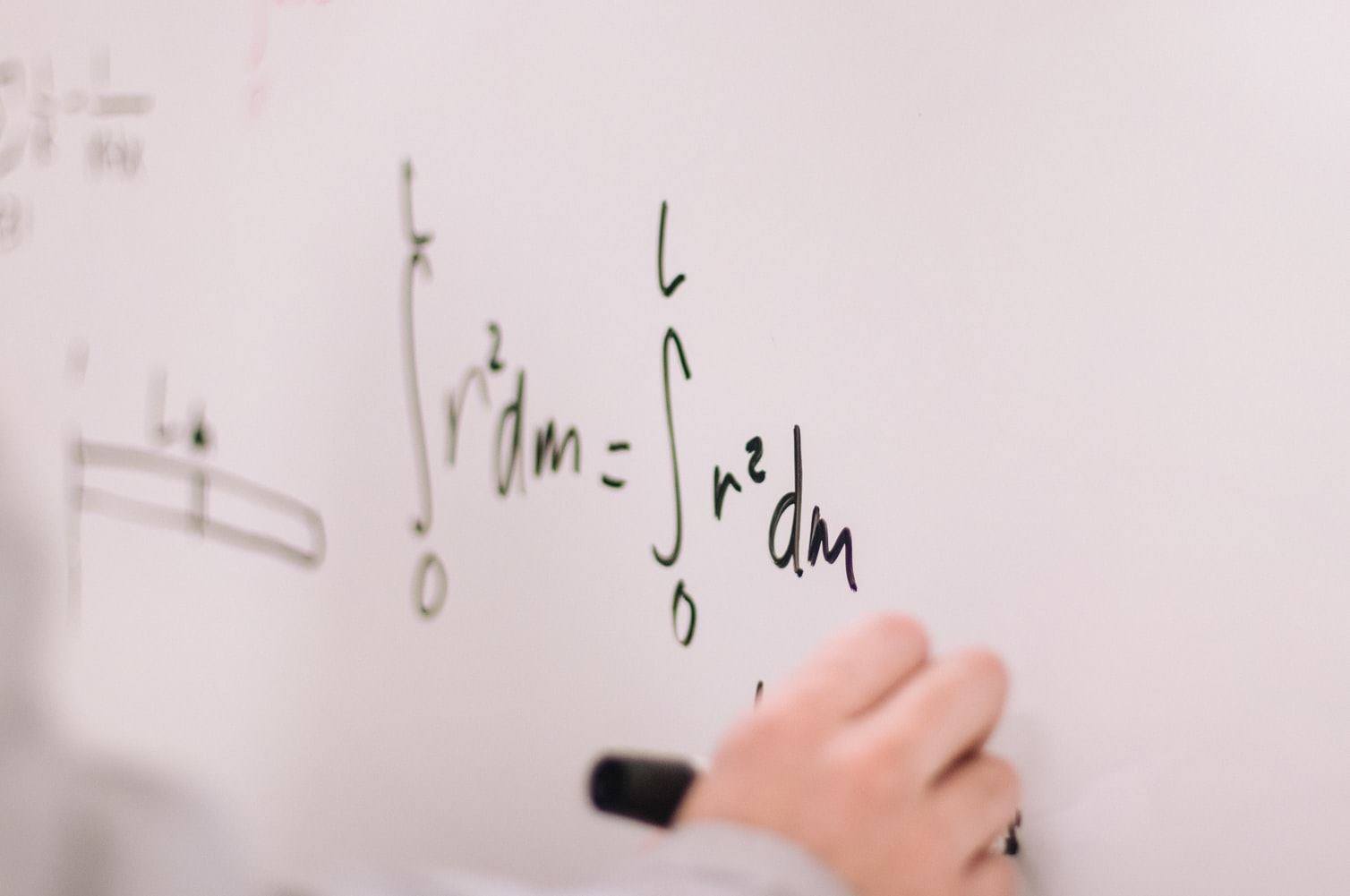
「採用力の公式」とは?
「採用力」とはその名の通り企業が人材を採用するにあたり保有する力です。採用は一般的に採用環境が大きく影響します。
例えば求人倍率が高ければ採用がしにくく、低ければ採用がしやすい、などです。
しかし、同じ採用環境の下でも採用に成功する企業もあれば失敗する企業もあるのです。それはなぜかというと採用環境以外の要素、つまり企業の持つ「採用力」が大きな影響を与えているからです。
「採用力」は大きく3つの要素から構成されます。それは「企業力」「採用条件・待遇」「採用活動」の3つです。

まず「企業力」ですが、いわゆる従業員規模や売上高、資本力などの「企業規模」、会社の知名度や業界のイメージ、将来性や安定性などの「認知度・イメージ」、商品やサービスそのものや、技術力、販売力などの「商品・サービス」によって構成されます。採用における「企業力」の特徴はすぐに変えるのが難しいということです。
次に「採用条件・待遇」については、仕事内容や勤務地、勤務時間や職場の仲間などの「職場環境」、成長事業や新規事業を展開している、先のポジションが見えやすいなどの「将来への期待度」、給与や休日、福利厚生などの「賃金・福利厚生」によって構成されます。採用における「採用条件・待遇」の特徴は変えるまでに時間が必要なことが多いことです。
最後に、「採用活動」については大きく2つ、「採用広報」と「採用実務」について分けられます。
「採用広報」とは「何の目的で(why)」「誰に対し(who)」「どんなメッセージを(what)」「いつ(when)」「どこに(where)」「どうやって(how)」届けるかという、採用戦略に基づいた一貫性のある採用広報活動のことを指します。
「採用実務」とは応募受付から選考~内定、そして入社までの一連のプロセスに携わる、採用戦略に基づいた一貫性のある採用選考活動のことを指します。「採用活動」の特徴は手法の工夫次第で採用結果を大きく変えることができる可能性があるということです。
-1024x576.jpg)
「採用力の公式」から自社の採用戦略を問い直す
もしも自社が他社と比較して、「企業力」が高くなく、「採用条件・待遇」もそこまででない場合は、自社の「採用活動」を工夫する必要があります。「採用活動」を工夫する上で最も見直すべき点は何かというと「採用戦略」です。
現在、採用活動のトレンドとしてリファラル採用やアルムナイネットワーク、SNSやNOTE活用といったような手法論が多く叫ばれ、実際に手を付けている企業も多いですが、根本的に見直すべきは「採用戦略」です。
具体的には先の「採用広報」で触れたように「何の目的で(why)」「誰に対し(who)」「どんなメッセージを(what)」「いつ(when)」「どこに(where)」「どうやって(how)」届けるかという、そもそもの採用目的(why)を事業戦略と合致させているのはもちろん、求める人物像をもとに具体化させた採用ターゲット(who)を設定する時点で、「他社との競合優位性」「自社らしさ」を明確にする必要があります。
具体的手法は多数存在しますが、誰もが使えるシンプルでパワフルな手法は「3C」でしょう。

「3C」とは「Company(自社)」「Competitor(競合)」「Customer(顧客)」の頭文字である「3つのC」を分析する手法で、事業分析やマーケティングの際に用いられるフレームのひとつです。
これを採用に置き換えると、「自社」「採用競合」「採用ターゲット」となります。このフレームを用いながら、採用ターゲットが競合ではなく自社に惹かれる理由=「採用上の競合優位性」「差別化要素」を見つけ出し、場合によっては創り出していきます。
「採用上の競合優位性」「差別化要素」を見つけ出す上での観点も無数にあります。ひとつのヒントとしては先日の記事『強い組織や採用育成につながる「モチベーション・マネジメント」』にて紹介した「働く目的12のアングル」を活用するのも良いでしょう。

自社と採用競合になりえる企業との比較において、採用ターゲットに響く自社の要素は何なのか、逆に捉えれば自社の差別化要素からどんな人であれば採用ターゲットになりうるのか、を行き来しながら採用ターゲットと訴求ポイントを明確化していきます。この作業を丁寧にやることで「戦略的採用=戦いを略する採用活動」が可能になります。
さいごに
今回の記事では自社を「採用力の公式」の観点から捉え直し、自社にとって必要な「採用活動」とは何か?について考え直す機会になればと思い執筆いたしました。
多くの企業は大手企業や有名企業と比べ採用力が強くないと思います。そんな中でも、自社で働いてくれている仲間がいるならば、必ず自社に働く理由や魅力があるはずです。自社の魅力を問い直し、「採用戦略」を練り直すことによって「戦略的採用=戦いを略する採用活動」ができる企業が増えていけば、雇用のミスマッチが減り、企業と個人のベストマッチングによる事業成長が起こると信じています。
この記事が皆様の何かしらのお役に立てれば嬉しいです。